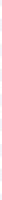即日退職は法律上可能?【労働者側、使用者側】 要件や、即日解雇は可能?
【この記事の法律監修】
森本禎弁護士(大阪弁護士会)
瀧井総合法律事務所

1 即日退職とは?
みなさんは、「即日退職」という言葉を聞いたことがありますか?
読者のみなさんの中には、ニュースなどでこの言葉を見聞きした、実際に即日退職をしたことがある、または現在即日退職をしたいと考えている方もいらっしゃるのではないかと思います。
この記事では、即日退職にまつわる法律上の問題について解説します。
1-1 即日退職は身近な問題
厚生労働省の統計によると、2023年の1年間で離職した労働者は約798万人で、全労働人口の約15.4%に達しています。つまり、日本の労働者の6~7人に1人が昨年1年間で離職している計算になります。
もちろん、この離職者の全てが即日退職によって辞めているわけではありませんが、従業員による退職代行業者への相談・利用は増加傾向にあり、即日退職はより身近な問題となっています。
1-2 即日退職の定義
法律上、「即日退職」という言葉はありませんが、「退職」という言葉は様々な法律で使われていますので、まず「退職」の定義について見ていきたいと思います。
労働基準法など、労働関係法令には「退職」という言葉を定義した規定はありませんが、厚生労働省は、労働者向けの資料などで、「退職」を「労働者の申出によって労働契約を終了すること」と定義しています。
これに対し、労働基準法を見てみると、22条1項で「退職の事由(退職の事由が解雇の場合…)」という規定があり、退職には「解雇」、つまり使用者(会社など)から一方的に雇用契約を解約し雇用関係を終了させる場合も含まれる言葉として使われていることがわかります。
このように、法律上「退職」は、労働者(従業員など)の申出によって労働契約(雇用契約)を終了させる場合だけでなく、会社が一方的に従業員との雇用契約を解約して雇用関係を終了させる解雇の場合も含まれるということになり、即日退職は、従業員が退職を申し出た、または会社が解雇を言い渡したその日のうちに雇用関係が終了すること、と定義することができます。
この記事では、即日退職をこのように定義した上で、解雇も含む即日退職は法律上可能なのか、その他にどのような法律上の問題があるのかなどについて解説していきます。
2 従業員が即日退職をすることは法律上可能?
結論から言うと、従業員が即日退職をするための要件・手続は、雇用契約の種類によって異なります。まずはじめに、雇用契約の種類について見ていきましょう。
2-1 雇用契約の種類
雇用契約は、法律上、「期間の定めがある雇用契約(有期雇用契約)」と「期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)」の2種類に分けられます。そして、有期雇用契約は、無期雇用契約と比較して、即日退職ができる場合が多くなります。
有期雇用契約は、文字どおり期間が定められている雇用契約のことで、例えば雇用契約書に「雇用期間の定めあり 令和6年4月1日~令和7年3月31日」という記載があれば、その契約は有期雇用契約となります。一般的に、アルバイト、パートタイマー、契約社員、派遣社員などのいわゆる「非正規雇用」において締結されることが多い契約です。法律上、有期雇用契約は原則として3年を超えてはならないとされています。
一方、無期雇用契約は、期間が定められていない雇用契約のことで、雇用契約書などに「雇用期間」という項目がなかったり、雇用契約書に「雇用期間の定めなし」と記載されていたりする場合、その契約は無期雇用契約となります。正社員といったいわゆる「正規雇用」において締結されることが多い契約です。
ただし、非正規雇用でも無期雇用契約となっている場合があります。例えば、派遣社員については、同一派遣先の同一部署への派遣は原則3年までと定められていますので、一般的には有期雇用契約となりますが、労働契約法により、契約期間が通算5年を超える場合は、労働者の申込みにより無期雇用契約に転換することが可能になります(これを「無期転換」などと呼びます。)。
このような場合は、派遣社員であっても途中から無期雇用契約に切り替わっています。また、その他の非正規雇用でも無期雇用契約となっている場合がありますので、一度雇用契約書の内容を確認することをお勧めします。
それでは、契約の種類ごとに順に見ていきましょう。
2-2 有期雇用契約の場合
労働基準法137条により、1年を超える期間の定めのある雇用契約を締結した従業員は、その雇用契約の期間の初日から1年を経過した日以降は、会社に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされています。
それでは、有期雇用契約であるものの、契約期間が1年以下、または契約期間は1年を超えているが働き始めてまだ1年が経過していない場合はどうなるでしょうか?この場合は、労働基準法137条の要件を充たしていないので、従業員の申出によりいつでも雇用契約を解消することはできません。
しかし、この場合でも、雇用契約に関する一般的なルールを定めた民法628条により、「やむを得ない事由」がある場合、従業員は、直ちに雇用契約の解除、つまり退職をすることができます。ただし、雇用契約の解除を求めた当事者の過失により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う可能性があることに注意が必要です。
どのような場合に「やむを得ない事由」があると認められているのでしょうか?「やむを得ない事由」があるかどうかは、最終的には裁判所が証拠によって認められる事実から総合的に判断することとなりますが、一般的には、従業員本人の病気やけが、家族の介護、妊娠や出産、給料の未払い、違法な長時間労働等劣悪な労働環境などがこれに該当すると考えられています。
従業員本人の病気やけが、家族の介護などについては、身体的な傷病だけでなくうつ病などの精神的な疾患も含みます。必ずしも医師の診断書などがなくても「やむを得ない事由」として認められる可能性はありますが、有力な証拠となりますので、もし入通院をしている場合は、医師に診断書を発行してもらい、保管しておくとよいでしょう。その際、医師から業務への復帰が困難と判断されている場合は、その点も診断書に記載してもらうと、「やむを得ない事由」の立証により役立ちます。このような診断書は、後で述べる無断欠勤を回避する上でも有効です。
なお、会社によっては、「やむを得ない事由」がなくても、一定の要件・手続の下で従業員の申出による退職を就業規則などで認めている場合もありますので、就業規則などを確認しておくとよいでしょう。
2-3 無期雇用契約の場合
無期雇用契約の場合、有期雇用契約の場合と異なり、労働基準法に雇用契約の終了に関する定めはありません。そのため、一般的なルールである民法の規定に従うことになります。民法627条1項は、当事者が雇用期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用関係は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了するとされています。つまり、この規定によって退職する場合は、即日退職はできないということになります。
ところで、会社によっては、「従業員は少なくとも1か月前までに退職を申し入れなければならない」という内容を就業規則などで定めている場合がありますが、この場合は2週間ではなく、1か月経過しないと雇用関係は終了しないのでしょうか?
この点に関し、裁判例は、この2週間の期間を延長する内容の定めは無効と判断しています。そのため、就業規則が2週間よりも前に退職の申出を求めている場合であっても、民法627条1項の規定に従い、申出から2週間が経過した時点で雇用契約は終了すると考えられます。
また、無期雇用契約の場合、試用期間を設けることが一般的ですが、試用期間中の従業員の申出による退職について、何か特別な制限はあるのでしょうか?解雇の場面で詳しく解説しますが、試用期間は、会社側の都合により設けられている制度ですので、従業員が自らの意思で退職する場合は特に影響はないと考えられます。通常の場合と同様、2週間前に退職の申出をすることにより、雇用契約は終了します。
2-4 有期・無期雇用契約に共通して即日退職できる場合
このように、民法627条の規定に従って無期雇用契約を終了させる場合は、退職の申出から最低2週間の期間の経過が必要となります。それでは、無期雇用契約の場合、即日退職は一切できないのでしょうか?
結論から言うと、無期雇用契約の場合でも即日退職できる場合があります。
それは、雇用契約の締結時に明示されている労働条件と実際の労働条件が異なる場合です。例えば、いわゆる「ブラック企業」に勤めている場合には、雇用契約締結時に提示された給与の金額や勤務時間が実際と異なることがあります。このような場合、労働基準法15条2項により即時に雇用契約を解除する、つまり即日退職することができます。この規定は、有期・無期どちらの雇用契約にも適用されますので、両種類に共通する即日退職の方法ということができます。
また、これまで述べてきた方法は、いずれも従業員が一方的に雇用関係を終了させる場合ですが、両当事者が合意して雇用関係を即日終了させることも法律上は可能です(これを「合意解約」と言います。)。双方の合意によるものですので、円満に退職でき後日の紛争を防止できるというメリットはありますが、会社が即日退職に同意しない場合もありますので、不確実な手段であると言えます。
2-5 即日退職のプロセスと円満に退職するコツ
一般的に両当事者が合意に達することが少ない即日退職を少しでも円満に行うコツは、法令、就業規則、雇用契約が定める要件・手続に従うことであると考えられます。衝動的に会社を「バックレ」てしまった場合でも、トラブルのリスクを最大限回避するため、これらの規定に則って行うようにしましょう。
これまで述べてきたとおり、有期雇用契約か無期雇用契約によって退職の要件・手続が異なりますので、まず、契約形態を中心に、就業規則や雇用契約をよく読み、現在の勤務先との雇用契約がどのような内容になっているかをチェックしましょう。
その後、退職の申出を行います。法律上、申出に決まった方法・様式はありませんので、口頭(電話)や書面の提出・郵送に加え、メールやLINEなどでも問題はないということになります。重要なのは確実に使用者側に退職の意思を伝えることと、後日申出の不達や言った言わないなどの争いが生じるリスクを可能な限り回避することです。
即日退職の場面では、心理的・時間的な余裕がない場合が多く、メールで退職を申し出ることもよくありますが、法律上は問題ありません。むしろ、メールであれば、費用をかけることなく確実に送信できますし、送信日時と文面を証拠として残しておくことができるという利点もあります。なお、できる限り会社との接触を避けたい場合は、退職代行業者を利用して申出を行うことも選択肢として考えられます。
内容についても決まったルールはありませんが、退職の申出であることを明確に表示することが法律上重要です。よく「退職願」や「退職伺い」と記載するケースがありますが、退職の申出は従業員からの一方的な意思表示ですので、会社の承諾や同意を前提とするような表現は控えた方がよいでしょう。一方、退職理由などについて詳しく記載する必要はなく、「一身上の都合」などと簡潔に記載することで全く構いません。ただし、できるだけ円満に退職するためには、内容面でも最低限の礼儀やマナーは心がけましょう。
有期雇用契約で所定の要件を充たす場合と無期雇用契約で労基法15条2項に該当する場合は即日、それ以外の無期雇用契約の場合は申出から14日が経過した時点で自動的に退職となります。もし有給休暇が残っている場合は、有給休暇を消化することにより、退職日まで出勤しないことも可能です。
3 会社が即日解雇することは法律上可能?
これまで、従業員の申出による即日退職の場合について解説してきました。
次に、会社が従業員との雇用契約を即日終了させる、つまり即日解雇することが法律上可能かどうかについて解説します。
3-1 解雇が認められる要件
即日解雇が可能かどうかについて述べる前に、そもそも解雇はどのような場合に可能なのかという点について解説します。
解雇は、会社などの組織が一個人である従業員から生活の糧を一方的に奪う非常に重い処分ですので、むやみにその権利が行使されないようにするため、法令や判例により、一定の場合に解雇が禁止されたり、解雇権の行使が厳しく制限されたりしています。
まず、以下の場合は、法律上明確に解雇が禁止されています。
<労働基準法>
- 業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
- 産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
- 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
<労働組合法>
- 労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
<男女雇用機会均等法>
- 労働者の性別を理由とする解雇
- 女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
<育児・介護休業法>
- 労働者が育児・介護休業などを申出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
引用:厚生労働省HP「労働契約の終了に関するルール 1 解雇」
また、解雇権の行使が制限される場合として、「解雇権濫用の法理」があります。これは、労働契約法16条によって認められる理論で、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。
そのため、労働者に何の落ち度もない場合はもちろん、勤務態度に問題がある場合や、業務命令や職務規律に違反するなど、労働者側に何らかの非がある場合でも、それにより直ちに解雇が認められるということはなく、「労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるか」など、様々な事情を考慮し、解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にのみ、正当な解雇権の行使として解雇が認められるということになります。また、解雇事由を含む退職に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければなりません。
3-2 即日解雇が可能な場合
解雇禁止事由に該当せず、就業規則の解雇事由に該当する事実があり、解雇を行う合理的理由が認められたとしても、原則として、少なくとも30日前に予告をしなければ、解雇することができません。そのため、この原則に従った場合、即日解雇はできないということになります。
ただし、30日分の平均賃金を支払うことにより(これを「解雇予告手当」といいます。)、予告期間をゼロにすることが可能ですので、即日解雇することは可能です。また、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合も、解雇予告は不要となるので、即日解雇は法律上可能となります。
3-3 無断欠勤による解雇
即日退職となるようなケースでは、従業員が、会社を「バックレ」てしまう、つまり会社で働くのが嫌になって無断欠勤をしてしまうということがよくあります。この場合、無断欠勤をしたことを理由に直ちに解雇されることはあるのでしょうか。
一般に、会社の就業規則は、欠勤の際は、申出を行って上司の承認を得たり、長期化する場合は医師の診断書を提出したりするなど、決められた手続を行うことを求めていますし、無断欠勤が一定の日数連続した場合を懲戒事由の1つとして定めています。
どれくらいの日数連続した場合に解雇されるかについては、就業規則に具体的に定められていることが多いですが、法律上は何日以上連続して無断欠勤したら解雇、という明確な規定はありません。
この点に関して、国家公務員の人事に関する規則を定めている人事院の「懲戒処分の指針について」は、官庁や地方公共団体だけでなく、企業も懲戒処分の基準を定める上で参考にされていますが、それによると、「正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。」と定めており、21日以上連続して無断欠勤した場合は解雇となる可能性が高いといえます。ただし、この基準はあくまで目安ですので、具体的な日数は勤務先の就業規則を確認しておくとよいでしょう。
もちろん、無断欠勤が連続20日以下であれば解雇されないかというと、必ずしもそうではありませんが、会社を「バックレた」からといって、直ちに解雇することは難しいということは言えます。ただし、無断欠勤の期間が短い場合であっても、減給や出勤停止など、解雇以外の懲戒処分を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
3-4 試用期間中の解雇
試用期間中に従業員を解雇する場合、通常の場合と比較して何か違いはあるでしょうか?
試用期間は、法令ではなく、就業規則や雇用契約などによって認められる制度で、従業員の適性に疑いがある事由が発生し、その改善が期待できない場合は解雇するという権利を会社に留保した雇用契約と考えられています。
このような試用期間を設けることは、その期間や内容が不合理と認められるものでない限り有効と考えられていますし、留保された解雇権を行使することにより、通常の場合と比較して広く解雇の自由が認められています。
しかし、この解雇権も、いつでも自由に行使できるというわけではありません。判例は、採用決定後における調査の結果や試用期間中の勤務状態などにより、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知った場合で、その従業員を引き続き雇用するのが適当でないという判断が客観的に相当であると認められる場合に限り、解雇権を行使できるとしています。
会社が試用期間中の勤務態度などを理由に従業員を解雇する場合は、このような制限があるということを認識した上で、解雇権行使の要件を充たしているかどうか、それを裏付ける証拠があるかどうかを十分に検討する必要があります。
3-5 実際に即日解雇された場合の対応
これまで、会社が従業員を解雇するためには様々なハードルをクリアする必要があることを述べてきましたが、それでも会社から即日解雇された場合、従業員の立場からはどうしたらよいでしょうか?
まず、解雇理由を把握することが重要です。解雇の予告を受けたり、実際に解雇されたりした場合、従業員は、解雇理由などを記載した書面を交付するよう会社に請求することができます。
会社は、従業員からそのような請求があった場合は、遅滞なく書面を交付しなければなりませんし、就業規則の解雇事由に該当する場合は、その具体的条項と該当する具体的事実を記載するなど、解雇理由を具体的に記載することが必要です。
従業員は、解雇理由に納得がいかない場合や、解雇事由に該当する事実があっても、解雇権の濫用ではないかと思われるような場合、解雇の手続に問題があるような場合は、解雇の無効を求めて裁判所に訴えを起こしたり、裁判外の紛争解決手続(ADR)による解決を求めることができます。
また、解雇自体は受け入れる場合でも、解雇予告手当など、法律上受け取る権利がある金銭などが未払いとなっている場合は、その支払などを会社に請求することも可能です。
3-6 退職勧奨と解雇の違い
これまで解雇について述べてきましたが、解雇によく似た会社の行為として「退職勧奨」があります。退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を勧めることで、一方的に雇用関係を終了させる解雇とは異なり、最終的に雇用関係を終了させるためには当事者間の合意が必要となります。
従業員が自由な意思で退職勧奨を受け入れて退職した場合は、適法に雇用関係を終了させることが可能です。しかし、長時間や多数回にわたる勧奨、相当期間一人部屋に配置するなどの措置を講じた上での勧奨、懲戒解雇をほのめかしての勧奨などは、従業員に不当な圧力をかけるものとして違法であり、過去には、退職の合意を強迫により取り消されただけでなく、従業員に対する慰謝料の支払も命じられた裁判例もありますので、会社が退職勧奨を行う場合は、違法な行為とならないよう十分に注意することが必要です。
従業員の立場としては、会社の言動が解雇やその予告なのか、あるいは退職勧奨なのかを見極めることが重要です。退職勧奨と認められるような内容であれば、従業員がこれに応じて合意しない限りは、雇用契約を終了させられることはありません。ただし、どちらかの判別が微妙な場合もありますし、違法な退職勧奨が行われる可能性もあるので、会社の言動を記録するなど、客観的な証拠を残しておくとよいでしょう。
4 即日退職にまつわる法律上のトラブル
これまで、解雇を含む退職について解説しました。即日退職はその他にも様々な法律上のトラブルを伴いやすく、特に、従業員が「バックレ」るケースでは、感情のもつれも生じ、トラブルに発展するリスクが高くなります。ここでは、実際にどのようなトラブルが起こり得るかについて解説します。
4-1 損害賠償請求される可能性はある?
これまで述べてきた要件・手続に従っている場合、その退職は適法ですので、その行為自体を理由として会社が従業員に損害賠償請求をすることはできません。
なお、就業規則や雇用契約に、雇用契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償の金額を記載したりするケースがありますが、このような規則・契約は無効であり、罰則の対象となります。
「バックレ」て失踪した場合など、法律上の要件・手続に従っていない退職や、有期雇用契約で「やむを得ない事由」が従業員の過失により生じたと認められる場合は、従業員が損害賠償責任を負う可能性があります。
一般的に、損害の発生や従業員の行為と損害の因果関係を立証することが難しいことなどから、会社が請求を断念することも多いと言われていますが、従業員が、会社から具体的な業務指示を受けていたにもかかわらず突然失踪したため、会社が請け負った業務を行うことができなかった事例において、受注代金から必要経費を差し引いた金額を損害として認め、その支払いを従業員に命じた裁判例もありますので、注意が必要です。
4-2 未払いの給与などはどうなる?
まず、即日退職した場合でも、契約期間中の給与や残業代などを支払われなければなりません。そのため、直近の給料日と次回給料日の間に退職の効力が発生した場合、直近の給料日から雇用契約終了日までの間は使用者に給与などの支払義務が発生します。
退職の場合、労働基準法23条1項により、使用者は、労働者の請求から7日以内に給与など使用者が受け取る権利がある金銭を支払わなければならないとされています。また、即日退職の場合、会社が一定の理由を根拠に給与などの支払義務について争うことがありますが、その場合でも、会社は全額の支払を拒むことはできず、争いがない部分の給与などについては、労働基準法23条2項により、従業員の請求から7日以内に支払われなければなりません。
また、会社が給与支払義務と会社が従業員に対して有している債権を相殺(減額)することは、賃金支払の5原則のうちの「全額払いの原則」に反し、認められないとされていますし、従業員が前借りをしていた場合、会社がその返還請求権と給与などの支払義務を相殺することも法律で禁止されています。
4-3 ボーナス(賞与)はどうなる?
給与とは異なり、ボーナスに関する法令上の規定はありません。そのため、退職時にボーナスが支払われるかどうかは、就業規則や雇用契約書などの規定に従って判断することになります。
この点に関して、就業規則や雇用契約書に、「支給日に在籍した者のみにボーナスを支給する」という内容の規定が設けられていることがありますが、このような規定がある場合、支給日前に退職した従業員にはボーナスは支給されないということになります。
このような規定がない場合は、就業規則や雇用契約の規定により算出された金額のボーナスを受け取ることができます。通常は退職日までの日割り計算で支給されます。
4-4 退職金はどうなる?
退職金も、ボーナスと同様、法令上の規定はなく、就業規則や雇用契約などに基づいて支給されていますので、即日退職した場合に退職金が支払われるかどうかは、就業規則や雇用契約等の規定に従うことになります。
ただし、ボーナスと異なり、退職金は給与の後払的性質を有していると考えられているので、支払日・方法について労働基準法の関係規定の適用を受けるのではないかが問題となります。
厚生労働省の通達は、退職金の場合、あらかじめ就業規則などで支払時期を定めている場合は、その時期までに支払えば足り、従業員の請求から7日以内に支払わなくてもよいとしています。これは、給与と異なり退職金は金額が大きく資金準備に時間が必要であることや、外部の積立制度を利用している場合は、その取崩手続に時間がかかることなどを理由とするものです。
4-5 未消化の有給休暇はどうなる?
年次有給休暇(有給休暇)は、雇用契約の種類や雇用形態を問わず与えられることとなっており、6か月間以上勤務し、出勤日数がその8割を超える場合、勤続年数に応じ、原則として10~20日の有給休暇を与えなければならないとされています。それでは、退職時に未消化の有給休暇がある場合、その権利はどうなるのでしょうか?
有給休暇は、雇用契約があることを前提とする従業員の権利ですので、雇用契約終了時に消滅すると考えられています。即日退職の場合、申出即退職となるため、有給休暇をすべて消化できずに雇用契約が終了する可能性が高くなります。
その場合、未消化の有給休暇を会社に買い取ってもらうことは可能でしょうか。有給休暇は、従業員に実際の休息を与えることを目的としていますので、原則として有給休暇の買取は違法と考えられていますが、退職後は従業員に実際に休息を与える必要がないため、例外的に未消化の有給休暇の買取を行うことが認められています。
就業規則や雇用契約などに規定がなくても、会社と従業員との間の合意により買取を行うことは可能です。しかし、トラブル防止や退職する従業者間で取扱いに違いが生じないようにするため、就業規則や雇用契約などに買取を認めることや条件を明記しておくことが望ましいと考えられます。
また、引継ぎなどを理由として会社が有給休暇の消化を認めないケースがありますが、有給休暇は従業員が請求した時期に与えなければならないとされていますので、このような措置は違法です。ただし、会社は、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、他の時季にこれを与えることができます(これを「時季変更権」といいます。)。なお、年間10日以上の有給休暇が与えられる労働者については、使用者はそのうち5日間を実際に取得させなければなりません。これらの義務は労働基準法39条に定められており、違反した場合は罰則もありますので、注意が必要です。
4-6 貸与物品や職場内の私物はどうなる?
パソコンや携帯電話などの端末、身分証、健康保険証、セキュリティカードなど、会社から従業員に貸与されている物品については、会社に所有権があるので、退職時に会社に返却する必要があります。もし返却しなかった場合、損害賠償請求など民事上の責任を追及される可能性があるほか、場合によっては業務上横領などの犯罪が成立することもあるので、必ず返却するようにしましょう。
返却は郵送や宅配便でも構いませんが、可能であればあらかじめ返却すべき貸与品をまとめておき、会社から請求される前またはその直後に発送するとよいでしょう。会社によっては、貸与品の返却を促す方法の1つとして、未払いの給与などを現金手渡しで支払うことを理由に来社するよう求めることがあるためです。
また、即日退職の場合、従業員が私物を会社に残したまま退職するということも珍しくありません。この場合、労働基準法23条は、給与などの金銭だけでなく、物品についても、従業員の請求があってから7日以内に返還しなければならないと定めています。
この場合も物品を郵送や宅配便で返却することは問題ありませんが、後にトラブルとなることが多いので、会社は、返還した物をリスト化し、それ以外に返還しなければならない私物はない旨の誓約書に署名をして送り返してもらうなどの措置を講じておくのが望ましいと考えられます。
5 まとめ
これまで見てきたように、即日退職・解雇は、一定の場合に行うことが可能ですが、法令、就業規則、雇用契約など数多くの関連規定をよく検討する必要がある上、従業員の生活や会社の業務に与える影響の大きさ、当事者間の感情的なしこりや不満なども相まって、様々な法律上の問題・トラブルが発生しやすい場面であると言えます。そのため、両当事者だけでは解決が困難になるケースや長期化するケースも決して少なくありません。
最近では、従業員による退職代行業者への相談・利用件数が増えていますが、会社が応じないケースもあり、従業員の代理人として会社との交渉やトラブルの解決といった法律事務を行うには、弁護士の関与が必要となります。
また、会社の立場から見ても、即日退職・解雇の場面では、時間的余裕がない中で様々な法律上の義務を履行・遵守していく必要がありますし、このような事態が発生してもすぐに対応できるような態勢の整備も必要不可欠です。
そのため、従業員側・会社側ともに、即日退職・解雇の問題が生じた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
関連記事
今すぐ仕事を辞めたい方へ!今すぐ仕事を辞める方法|退職代行ナビ
約3割が期間工を即日退職!人事が教える上手な退職の仕方とバックレのデメリット|しごとウェブ転職
ストレスが原因で即日退職できる?やむを得ない理由があれば即日退職可能!|退職サポーターズ