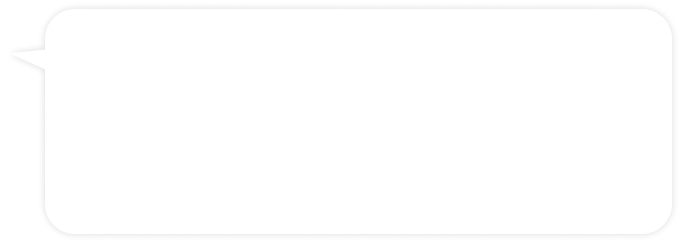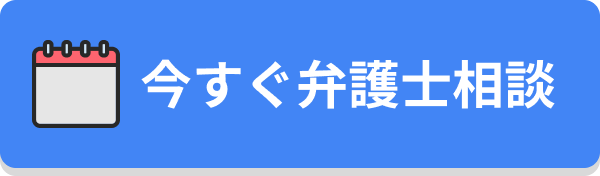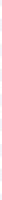法定相続分とは?遺留分とは何が違う?それぞれの違いと計算方法を解説
遺産を相続する人には、法定相続分が決められています。一体誰がいくら相続するのか?なぜその額なのか?
この記事では法定相続分の知りたいところをわかりやすく解説し、遺留分と法定相続分の関係についても紹介します。

遺産を相続する人には、法定相続分が決められています。一体誰がいくら相続するのか?なぜその額なのか?
この記事では法定相続分の知りたいところをわかりやすく解説し、遺留分と法定相続分の関係についても紹介します。
・法定相続分は相続順位に基づき決められる
・順位が同じ法定相続人は平等に法定相続分を持つ
・遺留分も相続順位に基づいて決められる
法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合をいいます。
法定相続人の順位により法定相続分は異なり、同順位の法定相続人が複数いる場合には、その人数によって相続分を均等に分割するようになります。
人が死亡して遺産相続が始まると、遺言がある場合には、相続分はまず被相続人の遺言によって指定されます。これを指定相続分といいます。指定相続分は、相続人の遺留分を害さなければ、どのようにでも割り振りができます。
この遺言の指定がない場合は、遺産分割協議が行なわれ、この法定相続分に基づいて遺産の分割が行なわれるのが一般的です。
相続順位ごとに認められる法定相続分
誰が法定相続人になるかによって、法定相続分は異なります。
法定相続人とは、民法の規定により相続する権利を持つ人のことをいいます。
法定相続人になれるのは、基本的に配偶者と一定の血族のみです。
配偶者は常に相続人になりますが、戸籍上の夫婦である必要があります。内縁の妻は婚姻関係にないので法定相続人にはなれません。
配偶者以外の相続人には順位があり、これを相続順位といいます。相続順位は以下のようにまとめられます。
|
配偶者 |
常に相続人 |
|
第1順位 |
・子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合は曾孫などの 直系卑属 |
|
第2順位 |
・父母、父母がいない場合は祖父母などの直系尊属 |
|
第3順位 |
兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥、姪 |
*第1順位の相続人がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合は第3順位に、と相続人の順位が移動します。
法定相続人の法定相続分は、以下のとおりです。
|
相続人 |
法定相続分 |
|
配偶者のみ |
全て |
|
配偶者と子 |
配偶者:2分の1 子:2分の1 |
|
配偶者と父母 |
配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
|
子のみ |
全て |
|
父母のみ |
全て |
|
兄弟姉妹のみ |
全て |
血のつながりがあっても法定相続分がゼロの人、相続人でも本人が手続きできないケース
相続人は、被相続人の配偶者および血族関係のある人がなります。しかし、血のつながりがあっても、相続人になれる順番の問題などで相続人になれない人もでてきますし、相続人となっても自分で手続きができない人もいます。また、血族であっても、そもそも法定相続分のない親族もいるので注意が必要です。
以下、具体的に見て行きます。
1)代襲相続人がいる場合の父母など
被相続人の死亡時の親族が、配偶者と孫、父母の場合、配偶者と第2順位の父母が相続人になりそうですが、代襲相続の制度により、相続人になるのは配偶者と孫になり、父母は相続人になれません。
代襲相続とは、相続開始前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、後述する相続欠格や相続廃除によって相続権を失っているときには、その相続人の子が代わって相続人になる制度です。
2)特別養子の場合の実親と子
養子がいる場合、実子と同じように相続人になります。しかし養子縁組の方法により、普通養子と特別養子では、実親との継続関係が異なるので注意が必要です。
普通養子の場合、養親との親族関係が新たに発生し、実親との親族関係も継続します。したがって、養親と実親双方の相続人になります。
一方、特別養子の場合、養親との親族関係が発生することで、実親との親族関係はなくなるので、養親だけの相続人になります。
3)未成年者
相続人が未成年の場合は、相続や遺産分割などの法律行為を単独で行うことができないため、法定代理人をたてる必要があります。ただし、未成年者が結婚をしていれば、成人とみなされ単独で法律行為ができるので、代理人は必要ありません。
法定代理人は、通常は未成年者の親がなるのが一般的ですが、相続が「配偶者と未成年の子」であるような場合は、親と子の利益が相反するため、親は未成年者の法定相続人にはなれないので注意が必要です。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加します。
4)胎児
胎児も相続人になります。民法上、胎児はすでに生まれたものとして取り扱われるからです。ただし、この取り扱いは後日無事に出産した場合に限るので、流産、死産、中絶の場合には、最初からいないものとして相続人にはなりません。
5)行方不明者
相続人の中に行方不明者がいる場合は、相続人の戸籍の附票から住所を見つけて、直接本人宅を訪問する、手紙を出すなどして連絡を取ることが必要になります。どうしても連絡がつかないような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行います。裁判所が選定した不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
つぎに、血族であっても法定相続分のない人について見ていきます。
6)相続欠格者
相続欠格者とは、一定の欠格事由により法律上当然に相続の資格がないとされる者です。たとえば、相続財産を狙って被相続人や他の相続人を故意に殺害したような場合です。相続欠格事由に該当する人は、配偶者や血族であっても相続人にはなれません。
7)相続廃除された人
相続廃除された人とは、被相続人の意思により、遺留分を有する相続人の相続権を廃除された者です。被相続人を虐待したような相続人に対して、被相続人が家庭裁判所に相続排除の請求をするような場合です。なお、相続廃除の対象になる人は、配偶者と第一順位、第二順位の相続人に限られます。第三順位である兄弟姉妹は対象外になります。
8)相続放棄した人
相続放棄をした人とは、相続人が相続財産の承継を全面的に否認した場合です。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申立てなくてはなりません。
相続人の順位は、各家庭の家族構成により異なります。きちんとした確認が必要な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
法定相続分があるのになぜ遺産分割協議をするのか?
遺産分割協議は、被相続人の財産の分割方法について、相続人全員で話し合い決めることです。協議の成立には相続人全員の同意が必要になります。
したがって、法定相続分があっても、遺産分割協議ではこの法定相続分に拘束されずに、自由に相続分を決めることが可能です。相続人全員の合意があれば、自由な割合で遺産分割が行えるのです。
なお、被相続人の遺言がある場合は、この遺言にそった遺産相続が行われますが、この場合においても、相続人全員の合意があれば、遺言の分割方法に拘束されずに自由に遺産分割を行なうことが可能です。
法定相続分と遺留分の違いは?
相続の場面では、法定相続分と遺留分という言葉が頻繁に出てくるので混乱している人も多いことでしょう。しかし、両者は全く異なるものなので注意が必要になります。
ここでは、法定相続分と遺留分の違いについて解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない法律上保障された最低限の財産のことをいいます。
法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合をいいます。
まず、法定相続分は遺産分割協議など遺産を分割する場合の割合です。これに対し、遺留分は遺言や生前贈与などで一部の相続人が多く遺産を譲り受けた場合に、これを取り戻すための制度です。
以下、法定相続分と遺留分の違いをまとめました。
|
法定相続分 |
遺留分 |
|
|
問題となる場面 |
遺産分割のとき |
不公平な遺贈や贈与があったとき |
|
認められる人の範囲 |
配偶者 子や孫などの直系卑属 父母や祖父母など直系尊属 兄弟姉妹、甥や姪 |
配偶者 子や孫などの直系卑属 父母や祖父母など直系尊属 |
|
認められる順序 |
配偶者はつねに相続人 第1順位:直系卑属 第2順位:直系尊属 第3順位:兄弟姉妹、甥姪 |
なし |
|
対象になる財産 |
資産や負債を含む |
資産のみ |
|
時効の有無 |
なし |
遺留分侵害額請求の1年の時効 |
|
権利行使の方法 |
遺産分割 |
遺留分侵害額請求 |
遺留分は法定相続分より少ない
法定相続分と遺留分では「割合」もまったく異なります。表のように遺留分の割合は法定相続分よりも少なくなります。
|
相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
|
配偶者のみ |
全て |
2分の1 |
|
配偶者と子 |
配偶者:2分の1 子:2分の1 |
配偶者:4分の1 子:4分の1 |
|
配偶者と父母 |
配偶者:3分の2 父母:3分の1 |
配偶者:3分の1 父母:6分の1 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
|
子のみ |
全て |
子:2分の1 |
|
父母のみ |
全て |
父母:3分の1 |
|
兄弟姉妹のみ |
全て |
なし |
遺産分割協議で揉めたときは法定相続分を参考に
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、まずは法定相続分をよく理解しておくことが不可欠です。必ずしも法定相続分に拘束されるわけではありませんが、遺産分割を進めるための基準になるので円滑な話し合いが期待できます。
しかし、遺贈や生前贈与など、相続開始以前の問題も関連してくるので、話し合いだけで円満に解決できない複雑な状況に発展してしまうことが予想されます。遺産分割協議で揉めた場合は、法定相続分を参考にした遺産分割の提案をおすすめしますが、それでも解決できないような場合には、早い段階で弁護士に介入してもらうことをおすすめします。
まとめ
法定相続分で遺産を分けられたら効率的かもしれませんが、実際には寄与分や特別受益が問題となることや、物理的に遺産の分割が難しいこと、他には遺贈や生前贈与が絡むケースもあります。
法定相続分はあくまで一つの基準として、どうすれば相続人がそれぞれ合意できるのか?相続実務に強い弁護士と一緒に考えてみましょう。
関連記事