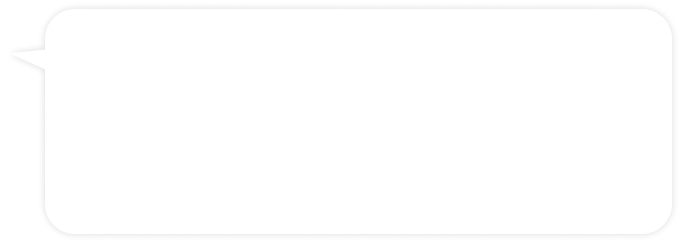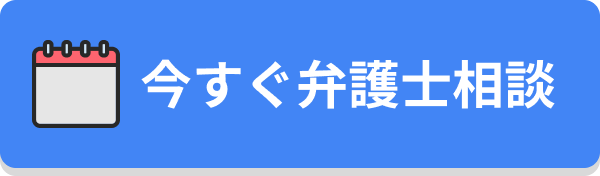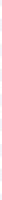離職票とは?発行・受け取りの手続きをまとめて解説
退職した労働者が失業手当を受給するためには、離職票の提出が必要です。この記事では離職票の申請から労働者が受け取るまで、労働者と使用者がそれぞれ何をすべきなのか紹介します。特に会社側は退職届を受け取ればそれで手続き終了ではありませんから気をつけてください。

・社会保険関連の手続きには離職票が必要
・離職票は意外と面倒、労働者は可能な限り早く申請すること
・トラブルになりそうなら弁護士に相談を
離職票はどんな書類で何に使うのか?
離職票とは、離職したことを証明する公的な書類です。正式には「雇用保険被保険者離職票」と呼びます。離職票は、退職した後に以下の手続きで必要になります
それぞれ解説していますので、参考にしてみて下さい。
離職票は社会保険の手続きで用いる
退職後は何かと手続きが必要です。特に大切なのが雇用保険のいわゆる失業給付(基本手当)を受給するための手続きです。会社を退職し、収入源がなくなってしまうと、貯金だけでは生活が厳しくなる場合もあるでしょう。
失業給付を受給する際、ハローワークに失業保険の申請をする必要があります。申請の際には、雇用保険の加入期間、勤務状況、退職理由等を証明する公的な書類である離職票は欠かせません。
離職票は転職で使うことがある
離職票は転職で使うことがあります。前職の会社を退職後、すぐに転職が決まって転職先の人事から、
「離職票を提出してください」
といわれるケースがあります。本来、転職先に離職票を提出する義務はないのですが、前職の会社に在籍していたことを確認するために提出を求められる場合があるでしょう。
手元にない等すぐに提出ができないとか、提出したくない場合には、
離職票が必要な理由を確認して必要に応じて別の書類を用意したり、提出できない理由や提出したくない理由を言うなどして提出しなくても良いか確認しても良いと思います。
また、離職票とは別に会社が発行する退職証明書があります。
利用目的は、離職票がまだ手元にない際、代用として失業給付や国民健康保険の手続きに使用されます。また、転職先が決まっている場合、その会社から前職の会社に在籍していたか確認するために提出することも。
ただし、退職証明書は離職票と違って、公的な効力は持ちません。ハローワークでの手続きを暫定的に退職証明書で行ったとしても、後日離職票が必要になります。
退職から離職票受け取りまでの流れ
退職後の手続きに必要な離職票は、退職してからすぐ手元に届く書類ではありません。
では、どのタイミングで離職票は手元にやってくるのか気になる方もいるのではないでしょうか?
退職後、今まであった収入が全くなくなってしまうため、失業保険をすぐにでも申請したいと考えている方もいるでしょう。
以下では退職から離職票受け取りの流れと、受け取った後の流れをあわせて解説します。
労働者が離職票の発行を申請
退職が決定した時点で、労働者側から会社に離職票の発行を依頼しましょう。退職届けを受理されるなど退職が決まった時点で手続きを進めてくれる会社もありますが、労働者側から申請するのがベターです。
申請方法は会社によって異なります。担当者に口頭で伝えて申請したり、書面で申請したり、メールで申請したりするなど様々です。勤務先のルールがあればそれに沿って申請してください。
離職票発行の申請が終われば、会社が離職票の発行に必要な離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)と雇用保険の資格喪失届を用意します。これらの書類は、労働者の退職日翌日から数えて10日以内に、会社側からハローワークへ提出する必要があります。
会社がハローワークから離職票の交付を受ける
会社が提出した離職証明書などの内容はハローワークで不備がないか確認されます。ここで、会社が提出した離職証明書などの内容に不備があれば差し戻しになります。
何事も問題がなければ、会社がハローワークから離職票-1と離職票-2の交付が受けられます。
その後、会社は退職した労働者に、ハローワークから交付された離職票を交付します。一般的には郵送で交付することが多いようです。会社が離職票を申請してハローワークから交付を受けるまで、さまざまな確認が入ります。そのため、交付を受けるタイミングは退職から10日~2週間前後はかかると考えておきましょう。
会社が作成する離職証明書の書き方
離職票の書き方は下記のとおりです。
- 被保険者番号に雇用保険被保険者番号を記入
- 事業所番号に雇用保険事業所番号を記入
- 離職者氏名に退職する労働者の名前を記入
- 離職年月日に退職する年・月・日を記入
- 事業所名・所在地・電話番号を記入(会社のゴム印で代用可)
- 離職者の住所または居所に退職する労働者が住んでいる住所、電話番号を記入
- 2枚目のハローワーク提出用に事業所の丸印の押印(1枚目は会社控え)
- 被保険者期間算定対象期間に、離職日から1ヶ月ずつさかのぼり記入
- 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数を記入
- 賃金支払対象期間に、給与の締め切り日から1カ月ずつさかのぼり記入
- 賃金支払対象期間における基礎日数を記入
- 賃金額に各月に支払われた賃金額を記入
- 備考には欠勤や休業手当の支払いなどがあった場合に記入
- 賃金に関する特記事項を記入
- 労働者の署名捺印
労働者が離職票を受け取りハローワークに提出
手元に届いた離職票は、そのままハローワークに提出しても、不備で返却されてしまいます。
離職票-1、離職票-2に退職した労働者が一部記入しなければならない箇所があるので、それぞれ説明します。
離職票-1の記入箇所
A4サイズである離職票-1の記入箇所は、以下の2点です
- マイナンバーカードや通知カード(※1)に記載されている個人番号
- 求職者給付等払渡希望金融機関指定届にある払渡希望金融機関(※2)
※1:通知カードの新規発行は2020年5月25日に廃止されています。
※2:失業手当の振込先銀行口座を記入してください。
離職票-2の記入箇所
続いて、A3サイズの離職票-2の記入箇所は、少し多くなります。
- 離職理由(離職者記入欄)
- 具体的事情記載欄(離職者用)
- 離職者本人の判断(会社側の離職理由について異議の有無)
- 署名・捺印
2と3は、しっかり確認しましょう。労働者労働者側に交付される離職票-2は、会社が記入した離職理由が記入された状態です。会社側の記載内容に相違がなければ、同じ離職理由を記載してハローワークに提出してください。
万が一2、3の内容が会社と異なっていると、失業給付の手続きはストップします。
この場合、ハローワークは会社側に事情を確認したり、労働者側から事情を確認したりしてを細かく調査し、最終的な判定がなされます。
ハローワークに失業手当の受給申請をしよう
失業給付は、雇用保険に加入している労働者(被保険者)が離職後、再就職の意思があることが条件ですが、一定期間の生活費を補填する給付制度です。
収入がなく、不安定な生活を送らなくてすむよう、手元に離職票が届いたら、ハローワークに失業給付の受給申請をしましょう。
まとめ
離職票は労働者の生活を守るために必要な書類ですから手続きが面倒だからと先延ばしにしないよう、会社は注意が必要です。労働者も退職の際は可能な限り早く意思を伝えておきましょう。もし労務管理が面倒だったり離職票をめぐるトラブルになったりしたときは弁護士に相談しましょう。
労使共に快適な働き方ができるようなアドバイスが期待できます。
関連記事
もう悩まない!