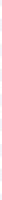変形労働時間制と36協定を結ぶことの意味の違いとは?
社会人経験がある人なら、「変形労働時間制」と「36協定」という言葉は、1度くらいは耳にしたことがあるでしょう。しかしその詳細について知っている方は少ないのではないでしょうか。「変形労働時間制は残業代がもらえない制度」「36協定を結んでいないと会社は労働者に残業させられない」このようにざっくり覚えているだけでは、大きな損をしてしまいます。「損をしない働き方」を身につけておきましょう。

変形労働時間制って36協定結ぶ必要あるの?
変形労働時間制を「残業代を出さなくていい制度」と理解し、36協定を「残業させるための協定」と理解していると、次のような誤解が生まれます。
「変形労働時間制を導入するときに、36協定は必要ない」
これは「100%間違った理解」とはいえないのですが、このような理解はとても危険です。万が一会社と争うことになった場合、労働問題では法律が大きく関与しています。
そのため、一般の方が一人で会社と争うのはかなり勝率が低いです。
あなたが望む結果にするためには弁護士の協力が必要不可欠です。まずは相談だけでも可能なので相談することをおすすめします。
それでは、解説をしていきます。
変形労働時間制と36協定(1) そもそも変形労働時間制とは

変形労働時間制と36協定との関係はとても難しいので、少しずつ制度の理解を深めていきましょう。
まずは変形労働時間制についてみてみます。
変形労働時間制とは① 労働時間の上限を”日・週”単位ではなく”月・年”単位で定める
労働基準法は、使用者は労働者を1日8時間を超えて働かせてはいけない、と定めています。
また、週40時間を超えて働かせてもいけません。さらに、最低週1日の休みを与えなければなりません。
ということは、労働者が最も長く働くパターンは「1日平均8時間働き、週5日間出勤する」か、「1日平均6.67時間働き、週6日間出勤する」しかありません。
しかし実際の労働パターンは、もっとたくさん種類があります。なぜでしょうか。それは、法律にはたくさんの例外があるからです。
その例外の1つが変形労働時間制です。
「仕事量が変動するので、1日8時間週40時間働かせることは無理!」という職場には、「じゃあ、1カ月間の労働時間をみて、平均して日に8時間以内になるならOKです」という例外が適用されるのです。
さらに「1カ月間でも無理!」という職場には「じゃあ、1年間の労働時間をみて、平均して日に8時間以内になるならOK」という例外もあります。
つまり、「1カ月間の中でつじつまが合えばよい」「1年間の中でつじつまが合えばよい」というルールです。
変形労働時間制とは② 閑散期と繁忙期の差が大きい企業に取り入れるメリット
このような例外ルールが生まれたのは、企業の事情を考慮したためです。
この例外ルールがあると、例えば、ある労働者を月の前半に週50時間働かせたけど、月の後半では週30時間しか働かせなかったといった場合、「その企業は労働基準法違反にならない」というメリットが生まれます。
具体的に見ていきましょう。
1日から15日までは激務だが、16日から月末まではほとんど仕事がなくなる、という事業場があったとします。
こうした職場で労働基準法の「原則」通りの運用をすると、1~15日分の残業代がかさむのに、16日~月末の仕事をしていない分の減給はできません。これで会社が「損」をします。
そこで、労働者が1~15日の間に1日8時間を超えて働いても残業代を支払わない代わりに、16日~月末までは早く帰宅できるようにするのです。
つまり、労働基準法の「例外」である変形労働時間制は、閑散期と繁忙期がある会社に配慮した、企業にとってメリットが大きい制度なのです。変形労働時間制とは③ 導入するにはある程度の条件を満たすことが必要
企業が変形労働時間制を導入するには、ある程度の条件を満たさなければなりません。
1か月単位変形労働時間制を就業規則により導入する条件を見てみましょう。
①就業規則に以下の内容を定める
②労働基準監督署に①を届け出る
労使協定または就業規則に定める内容は、次の通りです。
|
就業規則で定めるべき内容 |
就業規則への記載 |
|
変形労働時間制の対象となる労働者を定める |
「○○事業場は変形労働時間制とする」「次の者は変形労働時間制の対象とする」など。 |
|
対象期間と起算日を定める |
「毎月1日を起算日として、1カ月を平均して1週間当たり40時間以内とする」「毎年4月1日を起算日として、1年を平均して1週間当たり40時間以内とする」など。 |
|
労働日、労働時間 |
勤務シフト表や業務カレンダーなどで、何月何日に何時間の労働時間とするかを定める必要がある。 |
この基準を満たすことは、会社にとって「面倒なこと」です。
変形労働時間制と36協定(2) 36協定についてもう一度おさらい

企業が変形労働時間制を導入するには、就業規則で所定の内容を定めるなどの手続きをしなければならないことを紹介しました。
これは、労働基準法32条の2で定められています。
同条で「残業をさせる場合36協定を締結しなければならない」とは書かれているわけではないので、変形労働時間制と36協定は一見関係がないようにも思えます。36協定とは① 法定時間外に労働をさせる場合に締結しなければならないもの
労働基準法36条には、次のように書かれてあります。
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
これを要約すると、労働者を「1日8時間、週40時間」を超えて働かせるには、労働組合か労働者の代表と、書面による協定を結びなさい、ということになります。
そして、この労働基準法36条では「第32条から第32条の5まで…に関する規定にかかわらず」と規定されているので、32条の2などの変形労働時間制の場合にも同条が適用されるということになります。
例えばある企業が、労使協定や就業規則で「毎月1日から10日は1日10時間勤務、21日から30日は1日6時間勤務」と定めたとします。
このとき、1~10日の間に1日でも11時間勤務をさせたり、11日~30日の間に1日でも10時間勤務をさせたら、残業時間が発生するので、もし36協定を結んでいなかったら労基法違反となってしまいます。
なので、「変形労働時間制を導入する企業は当然のように36協定も結んでいる」のです。36協定とは② 36協定を結んだらいくらでも残業させて良いわけではない
とはいえ、36協定を結び、残業代を支払っていれば、何時間でも残業させていいわけではありません。
残業時間の上限時間には細かい区分けがありますが、ここでは「1年単位」をみてみます。
36協定を結んだ企業が、労働者に残業を課すことができる上限時間は、1年間360時間です。
ただ、変形労働時間制の対象となっている労働者は1年間320時間の残業が上限となっています。
完全週休2日制で働く労働者は、1年間に約261日出勤(≒365日÷7×5)することになります。「毎日同じ時間残業する」と仮定すると、1日1.22時間(≒320時間÷261日)ということになります。
この数字を聞くと「え? 1日1.22時間(73.2分)を超えた残業は法律違反なの? そんなの毎日やらされているよ」と驚く方もいるのではないでしょうか。
ニュースでは、「月の残業時間が80時間だった!」などと報道されますが、法律から見ると、これがどれだけ「過酷なものか」がご理解いただけるかと思います。変形労働時間制と36協定(3) 目的を異にする全く別の制度
36協定と変形労働時間制の関係
国が「労働者を1日8時間、週40時間を超えて働かせてはいけない」と決めたのは、労働者の健康やワーク・ライフバランスについて考慮したからです。
しかし企業は「それでは十分な経済活動を展開できない」と異議を唱えました。
そこで1日8時間、週40時間を超えて働かせる方法、つまり36協定を制度化したのです。
一方の変形労働時間制は、「ある期間は長時間働かせるけど、別の期間は労働時間を短くするから、残業代を支払わなくてもいいよね」というルールです。
つまり、変形労働時間制は時間外労働を避ける制度であり、36協定は時間外労働をさせるための制度であり、両者は全く別の制度であるといえます。
もっとも、変形労働時間制は「残業はさせたいが、残業代は節約させたい」というニーズに応える制度なので、両制度はセットで採用されることが多いといえます。
36協定を締結で可能な残業には”割増賃金”を支払う義務がある
36協定は「残業をさせてもいい」ルールであり、「残業代を払わなくていい」ルールではありません。
会社側は残業代として労働基準法37条に基づき「割増賃金」を支払う必要があります。変形労働時間制を採用すれば会社側は割増賃金を節約することができる
一方の変形労働時間制では、1日9時間働いても10時間働いても、残業代が出ないことがあります。
1日10時間働いても残業代が出ないケースは、単位期間の週の平均労働時間が40時間以下となる場合です
変形労働制だからと言って残業代が発生しないわけではありません!
ですので、変形労働時間制を導入している会社でも、平均した労働時間が週40時間を超えれば、残業代は発生します。
しかしこうした勤務形態で働いていても、残業代が支払われないことがあります。
それは「社員たちが『変形労働時間制だから残業代は発生しない』と勘違いしていることを利用しよう」と会社側が考える場合です。
いわゆるブラック企業は、労働者の知識のなさや立場の弱さに漬け込み、変形労働時間制により残業代が支払われないなどと社員を勘違いさせる場合があるので注意が必要です。変形労働時間制で残業代が発生するケース

変形労働時間制の残業代(1)
1日8時間、1週40時間以内の所定労働時間が定められている週において、1日8時間、1週40時間を超える労働は時間外労働となります。
変形労働時間制の残業代(2)
1日8時間、1週40時間を超える所定労働時間が定められている週において、所定労働時間を超える労働は時間外労働となります。
変形労働時間制の残業代(3)
(1)(2)で時間外労働とならなかった労働時間の合計が、単位期間全体の法定労働時間を超える場合にはその超える部分も時間外労働となります。
就業規則に規定があればその計算方法に従う
また、就業規則に上記と異なる計算方法が定められている場合もあります。
そのような場合で、上の計算方法より残業代が高く出る場合には、その額を請求することが可能です。
変形労働時間制の残業代を請求する方法とは?
変形労働時間制の対象となっている労働者でも、残業代が出る仕組みはご理解いただけましたでしょうか。
しかし実際は、多くの労働者が残業代を「取りっぱぐれている」状態です。なぜでしょうか。
それは労働者が変形労働時間制と36協定に関する正しい知識を持っていないからです。
ブラックと呼ばれていない企業ですら、労働者から残業代の申請がなければ、「彼が居残って仕事をしているのは、自分のスキルが足りないと自覚しているからだろう。だから残業代を出さなくていいな」と考えがちです。
しかし、本来はスキル獲得に要する時間も使用者の指揮命令下にあれば労働時間であり、その仕事によって法定労働時間を超えて働いたら、残業代は支払われなければならないのです。まず就業規則をチェックし実際に残業代が発生していることを確認
残業代の「取りっぱぐれ」を防ぐには、就業規則のチェックと、実際の残業時間の把握、そして残業代が支払われていないことの確認が必要です。
まずは就業規則を入手しましょう。「総務部長の許可がなければ見ることができない」という会社もありますが、このようなルールは違法・無効です。
就業規則は、労働者がいつでも閲覧することが可能です。
残業時間の把握は、タイムカードのコピーがベストです。しかし、定時になったらタイムカードを押すことを強要され、そこから残業をさせられている場合はどうしたらいいでしょうか。
その場合、労働者自身のメモ帳に、勤務時間を書いておきましょう。また、自分のパソコンの起動時間のログを記録して印刷しておきましょう。それらでも十分「残業をした証拠」になり得ます。
残業代が支払われていないことを証明するためには、給与の明細書が必要です。直接交渉にいく or 内容証明郵便による請求
証拠を集めたら、会社側に残業代を請求しましょう。
しかし最初から「残業代を支払え!」と強く出るのは得策ではありません。
まずは「私の計算によると、残業代が足りないと思うのですが、再計算をお願いできないでしょうか」と穏便に言いましょう。
交渉相手は、給与計算をしている総務部または経理部の担当者となります。
もし給与計算担当者が応じてくれないのであれば、「次の手段」に打って出てください。
それは「内容証明郵便」です。
これを使うことにより、実労働時間で計算し直した残業代を請求したことを証拠として残すことができます。
ここまでやると、会社側も重い腰を上げてくれるかもしれません。会社が取り合ってくれないなら労働基準監督署へ
しかし筋金入りのブラック企業は、内容証明郵便でも動じません。もし会社が、かたくなに残業代の支払いを拒んだら、「奥の手」があります。
「奥の手その1」は、労働基準監督署に救済を求めることです。
まずは電話で「変形労働時間制の対象になっているが、決められた時間を超えて働いているのに残業代が支払われない」と伝えてください。
電話相談の次は、実際に労基署の職員と会って、実情を訴えることになりますが、その際、すべての「証拠」を持参してください。
きちんと証拠を押さえていれば、労基署は対応してくれるはずです。自分の会社の変形労働時間制に疑問があったら弁護士へ相談を
では、労働者自身が「ちゃんとした証拠」を集められなかったら、どうしたら良いでしょうか。
会社が就業規則のコピーを禁じたり、毎日の労働時間をメモ帳に記載していなかったら、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
そのときは「奥の手その2」を発動してください。弁護士に相談してください。
弁護士の中には、労働問題を専門にしている先生もいますし、「変形労働時間制の残業代問題」に詳しい方もいます。
そのような弁護士は、残業代をゲットするために「あなたがすべきこと」を教えてくれます。
弁護士費用の問題は、ひとまず置いておいて大丈夫です。というのも、多くの労働問題専門弁護士事務所は、「初回の相談は無料」としているからです。
つまり、その無料相談で残業代を回収できるかどうかの見通しが立つのです。
まとめ

労働問題は大きな社会問題になっています。過労自殺や長時間労働によるうつ病の発症は、悲劇です。
しかし、大きな社会問題の陰に、小さな問題が無数に隠れています。しかもほとんどの労働者は「確かに問題だけど、自分が少し我慢すればいいんでしょ」とあきらめてしまいます。
あきらめずに、まずは弁護士に相談してみてください。