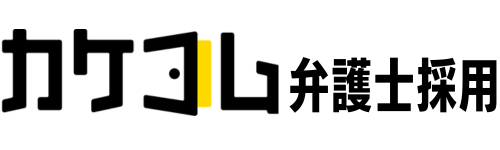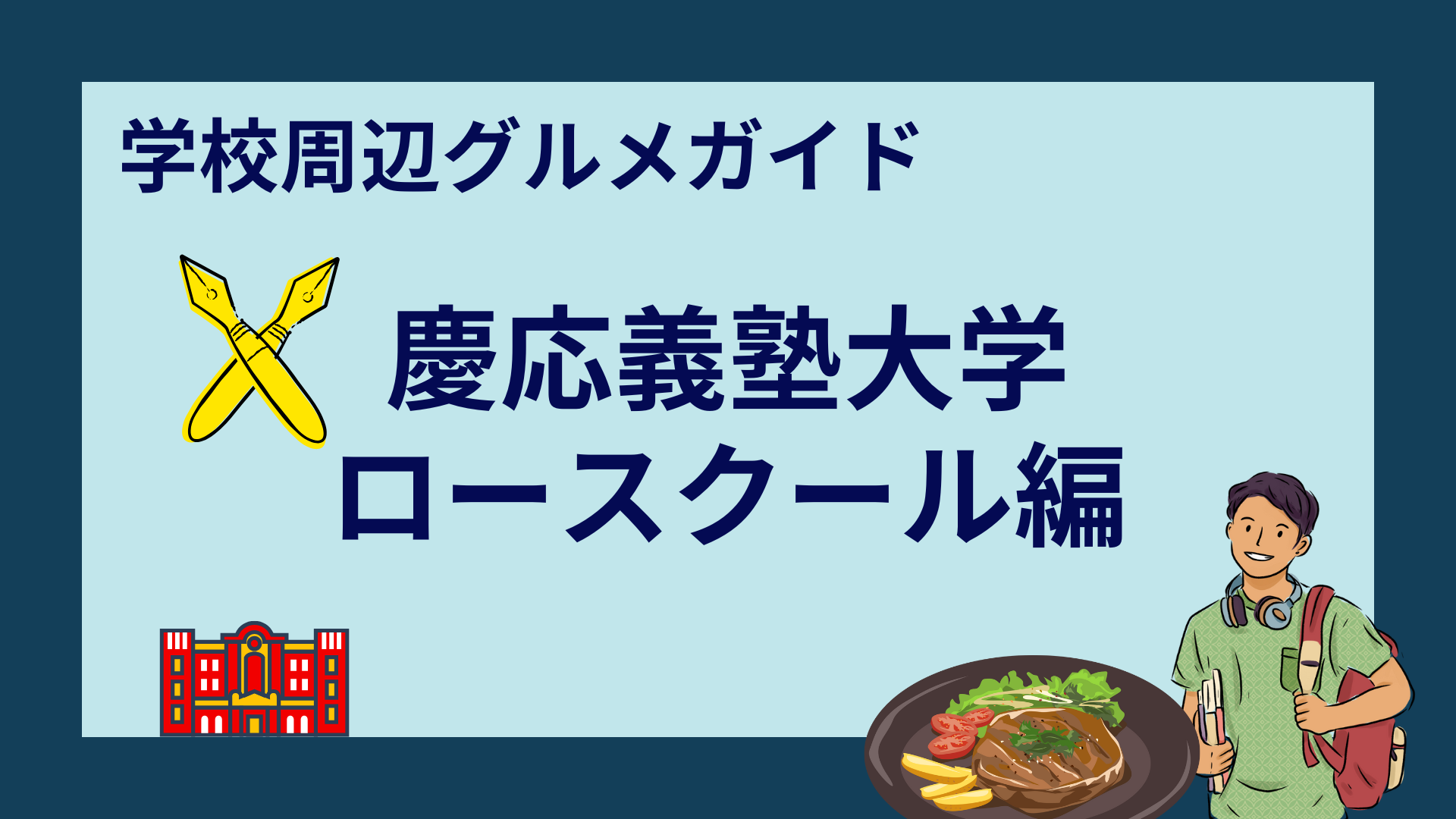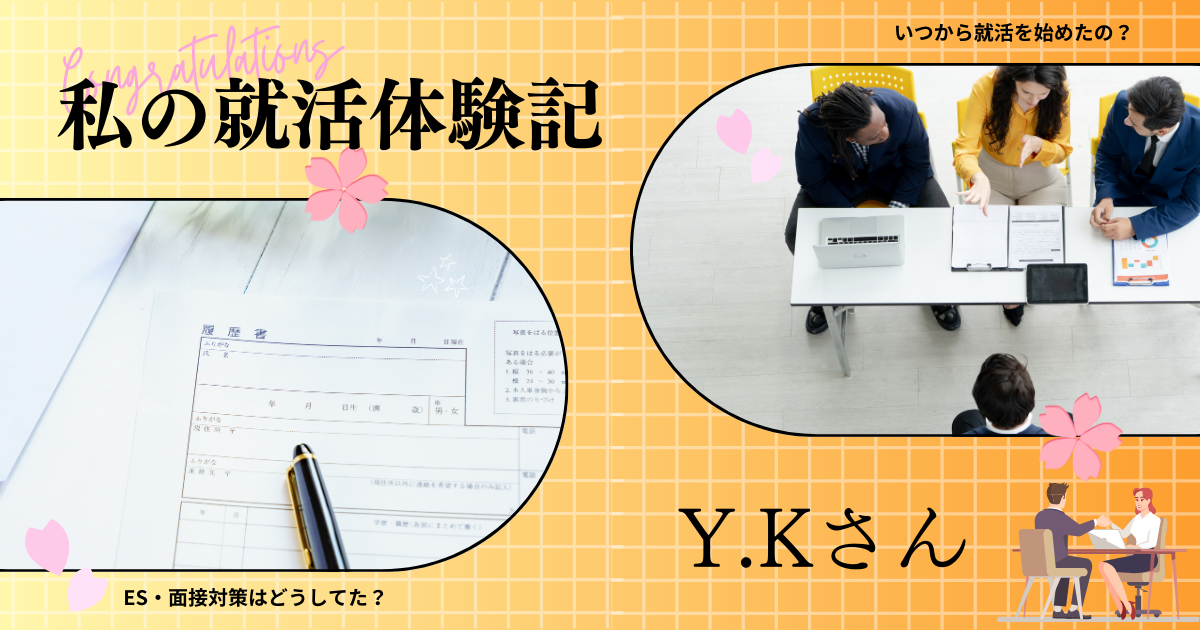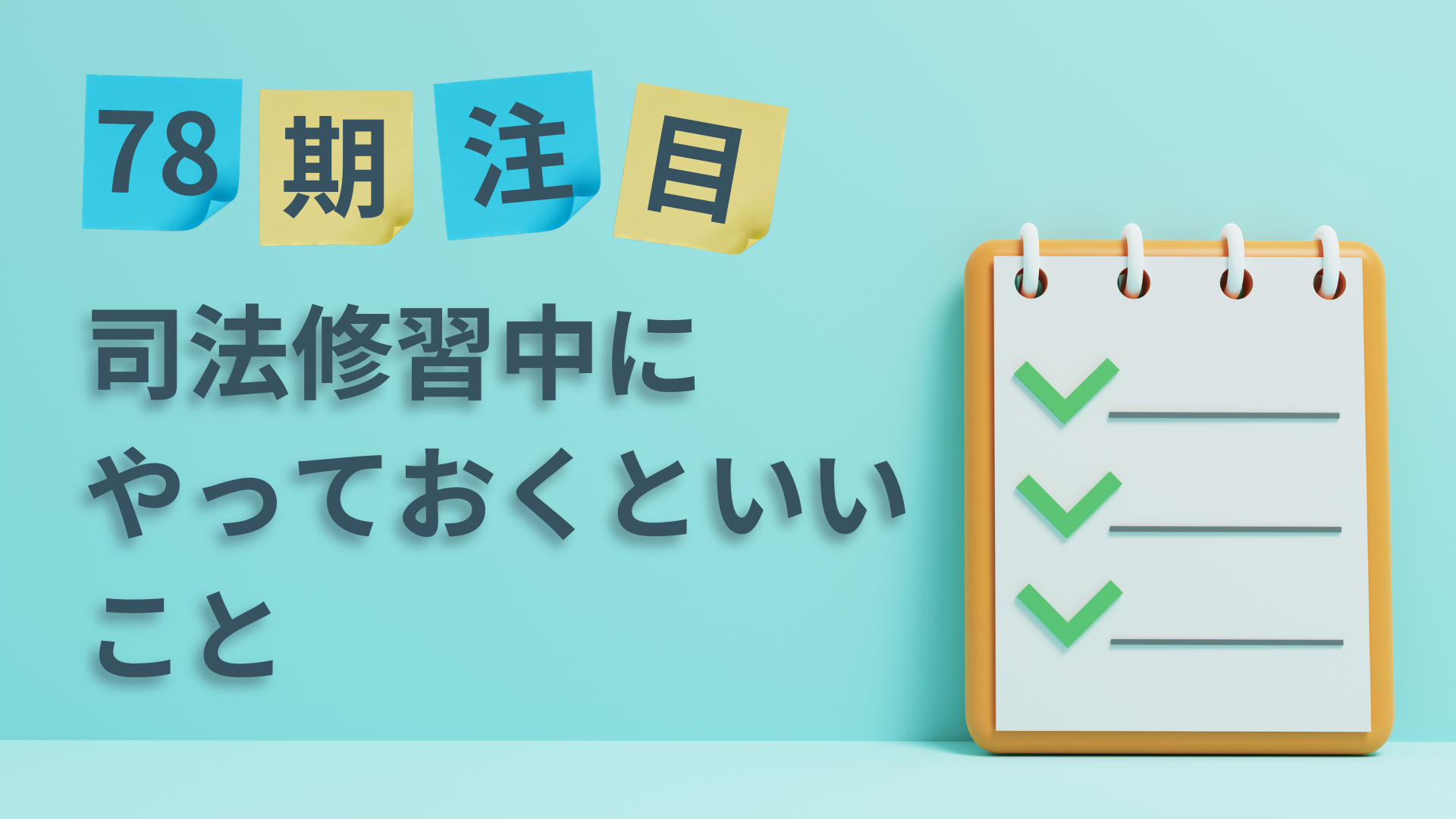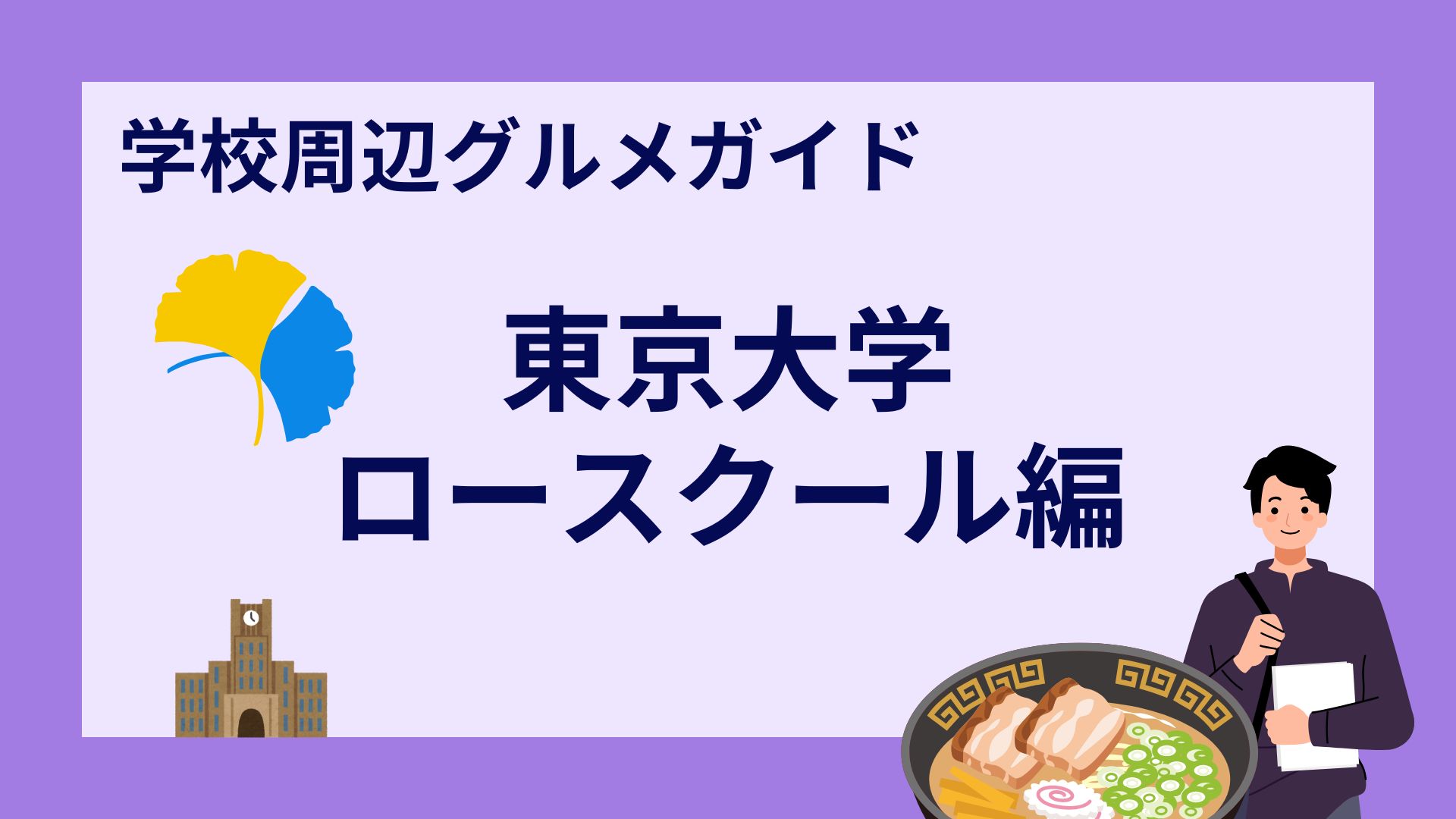- そもそも予備試験とは
- 予備試験の難易度
- 予備試験のメリット、デメリット
- 予備試験の3つの試験
- 終わりに
そもそも予備試験とは
予備試験は誰でも受けることができます。
試験は①短答式試験②論文式試験③口述試験の3つから構成されています。
これらの試験は受験者全員が受けられるわけではなく、①、②、③と順番に受からなければ次の試験を受けることはできません。それぞれの試験については後ほど詳しく説明します。
そして口述試験に合格すれば、晴れて司法試験の受験資格を得ることができます。
なお予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験のすべてを一度に合格しなければなりません。
短答式試験は合格したが論文式試験は落ちてしまったという場合、次に予備試験に挑戦する場合は再度短答式試験から受験する必要があるのです。
予備試験の難易度
では予備試験の難易度は具体的にどのようなものなのでしょうか?
| 年 | 出願者数 | 短答式試験 | 論文式試験 | 口述試験 | 最終 合格率 |
| 合格率 | 合格率 | 合格率 | |||
| 令和5年 | 16,704人 | 20.0% | 19.0% | 98.3% | 3.6% |
| 令和4年 | 16,145人 | 21.8% | 17.8% | 98.1% | 3.6% |
| 令和3年 | 14,317人 | 23.2% | 18.2% | 98.1% | 4.0% |
| 令和2年 | 15,318人 | 23.8% | 19.0% | 95.7% | 4.2% |
| 令和1年 | 14,494人 | 22.9% | 19.1% | 96.4% | 4.0% |
最終合格率が一桁台であることから予備試験の難易度が高いことが分かります。
特に短答式、論文式では2割程度の合格率で、口述試験は大多数の人が合格していることから、短答式試験と論文式試験の対策が重要となってきます。
参考:法務省(https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00027.html)
予備試験を受けるメリット、デメリット
メリット
- お金と時間がかからない
予備試験に合格すれば司法試験受験資格を得られるので、法科大学院に入学する必要がなくなり学費や時間を節約できます。
- 予備試験合格者の司法試験合格率が高い
| 予備試験合格者の司法試験合格率 | ||||
| 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
| 81.8% | 89.4% | 93.5% | 97.5% | 92.8% |
予備試験合格者の司法合格率は近年90%を越しており、圧倒的に合格率が高いのです。
難易度の高い予備試験に向けて勉強に励めば、安心して司法試験にも臨めます。
- 就職で他人に差をつけることができる
大手事務所は就職において、予備試験合格者を優先的に採用する傾向があります。また、予備試験合格者のみを対象としたクラークや説明会も開催されています。
クラークや説明会の詳細情報は、カケコム弁護士採用をご覧ください。
デメリット
- 難易度が高い
前述の通り、予備試験の合格率は非常に低く、簡単な試験ではありません。法科大学院ルートであれば、法科大学院を卒業さえすれば司法試験受験資格を得ることができます。
- 孤独な闘い!?
法科大学院を経て司法試験を受験する場合と違い、基本的に予備試験に向けて一人で勉強することになります。そのため受験仲間が作りにくいことがあるかもしれません。人脈が仕事の受注につながる場合もあるため、学校で仲間を作る代わりに積極的に交流の場に出て、勉強仲間や弁護士の方とのつながりを構築することが大切です。
カケコムでは法曹を目指す学生と法律事務所を結ぶため、定期的にカンファレンスやカジュアル面談を定期的に開催しています。ひとつの人脈構築の手段としてぜひご利用ください。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。【法律事務所 カジュアル交流イベント 一覧】
予備試験の3つの試験
①短答式試験
<試験科目>
憲法、行政、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の7科目(以下、7科目を合わせて法律基本科目といいます)と一般教養科目の全8科目です。
一般教養科目では人文科学、社会科学、自然科学及び英語の分野から、40問程度の問題が出題され、その中から、20問の問題を選択して解答します。
法律基本科目はそれぞれ30点、一般教養科目は60点配点で満点270点です。
<時期>
毎年7月中旬から下旬までの間の時期に1日で実施し、8月頃までに合格発表が行われます。
<問題数>
各科目いずれも10問ないし15問程度で、各科目30点満点です。
合格ラインは例年160~170点程度です。
<試験時間>
憲法と行政法で併せて1時間、民法、商法と民事訴訟法で併せて1時間30分、刑法と刑事訴訟法で併せて1時間です。
一般教養科目は1時間30分となっています。
②論文式試験
<試験科目>
法律基本科目7科目のほか、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)のうち受験者のあらかじめ選択する1科目(以下、選択科目といいます)並びに法律実務基礎科目民事、法律基礎科目刑事の合計10科目です。
各科目それぞれ50点配点で、満点は500点です。
<時期>
毎年9月頃までに2日間で実施し、12月頃までに合格発表が行われます。
<問題数>
各科目いずれも1問です。
<試験時間>
憲法と行政法で併せてて2時間20分程度、民法、商法と民事訴訟法で併せて3時間30分程度、刑法と刑事訴訟法で併せて2時間20分程度です。
法律実務基礎科目民事、法律実務基礎科目刑事は併せて3時間程度で、選択科目は1時間10分程度となっています。
③口述試験
<試験科目>
法律実務基礎科目(民事、刑事)について行うものとされています。
出題範囲は、論文式試験の法律実務基礎科目と同様で、民事及び刑事について実施し、法曹倫理は、民事及び刑事の各分野における出題に含まれるものとされています。
配点は、民事及び刑事について同一です。
口述試験については、法務省から出題方針が発表されているのみで、問題が公表されていません。
<時期>
毎年、短答式試験及び論文式試験を実施した年の翌年の1月頃までに実施し、2月頃までに合格発表が行われます。
参考:法務省(https://www.moj.go.jp/content/001406522.pdf)
終わりに
ここまで予備試験について説明してきました。予備試験が難しい試験だということは言わずもがなですが、後に受験することになる司法試験の対策としても弁護士を目指す方には受験をお勧めしたいです。
予備試験合格者の方を対象とした法律事務所の説明会情報やクラーク情報を随時更新予定ですので、ぜひカケコム弁護士採用を配信登録してお待ちくださいね!