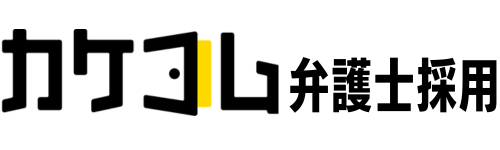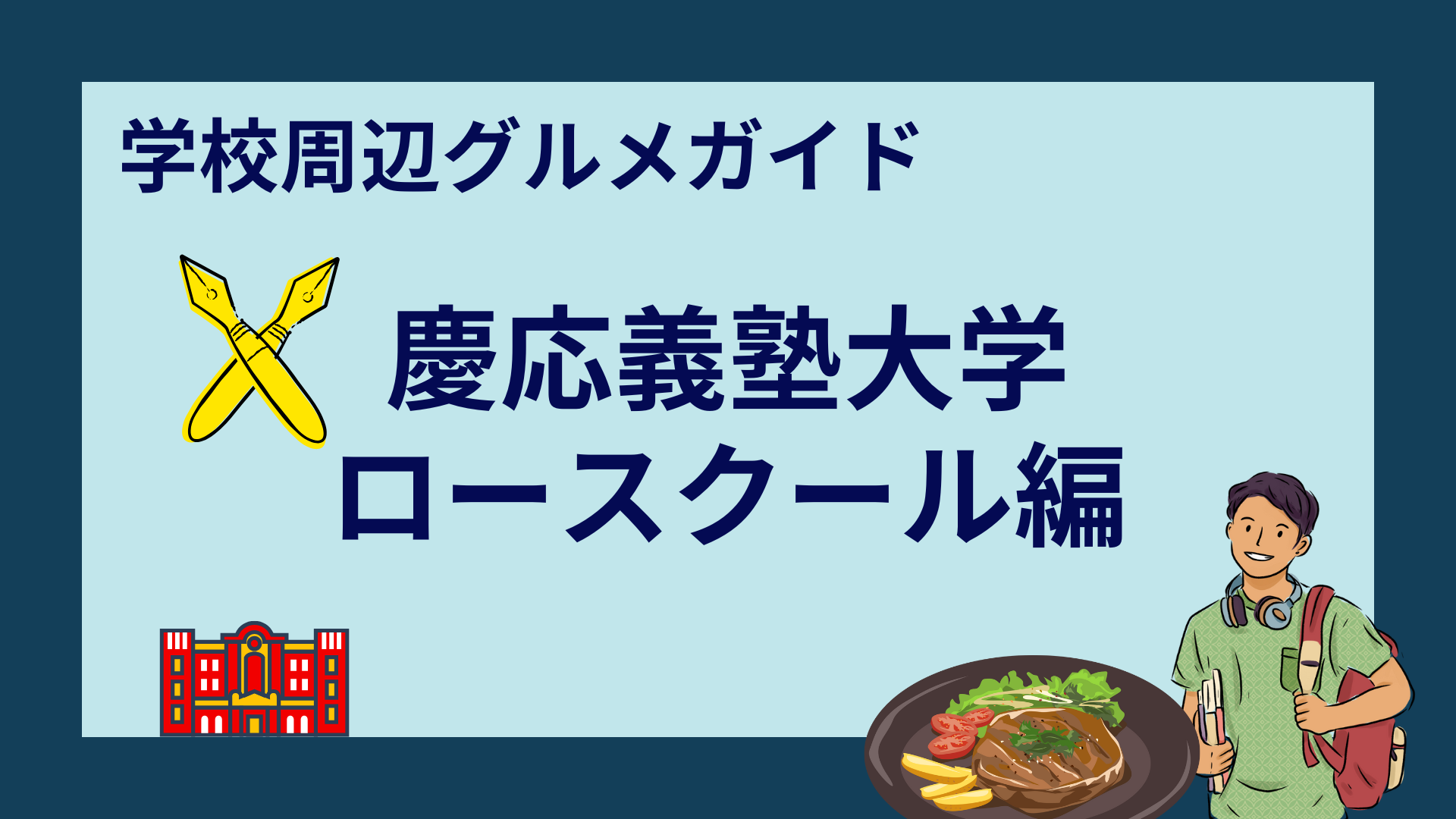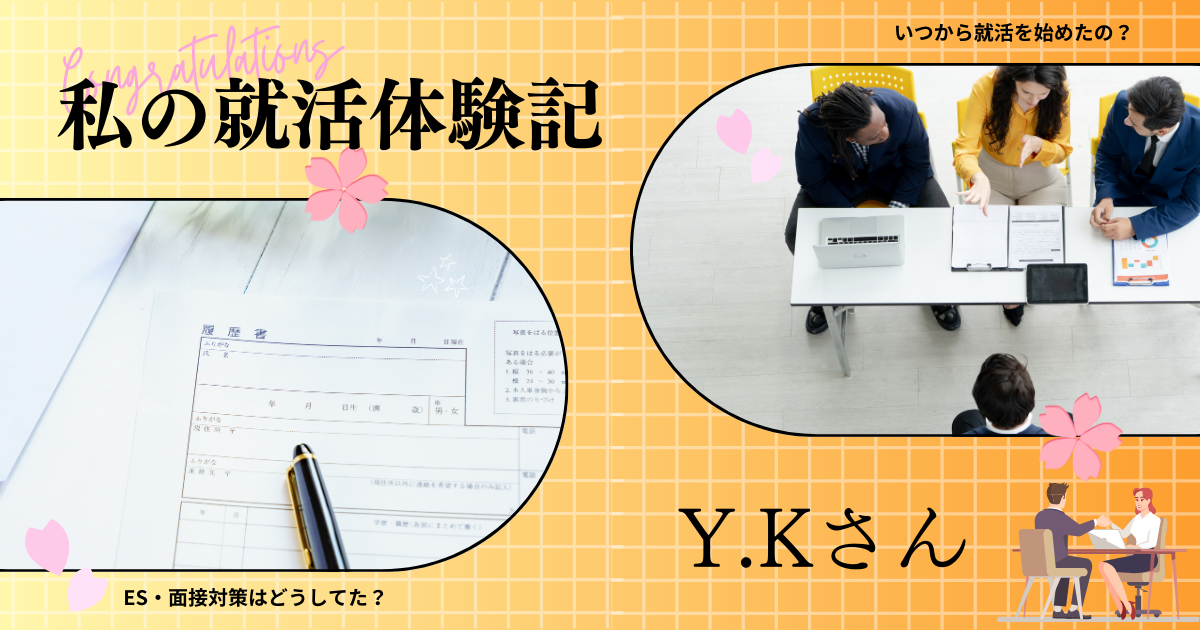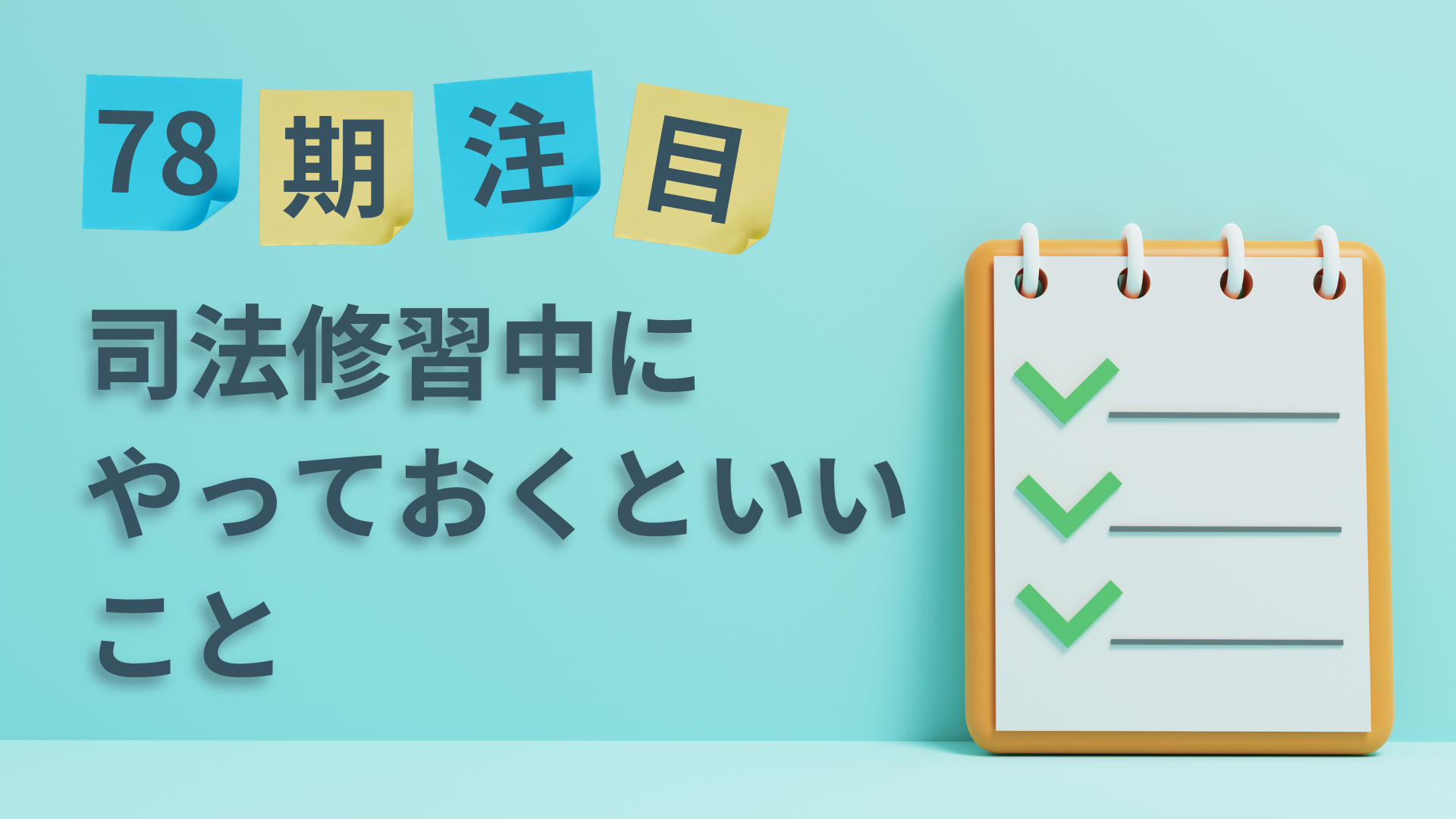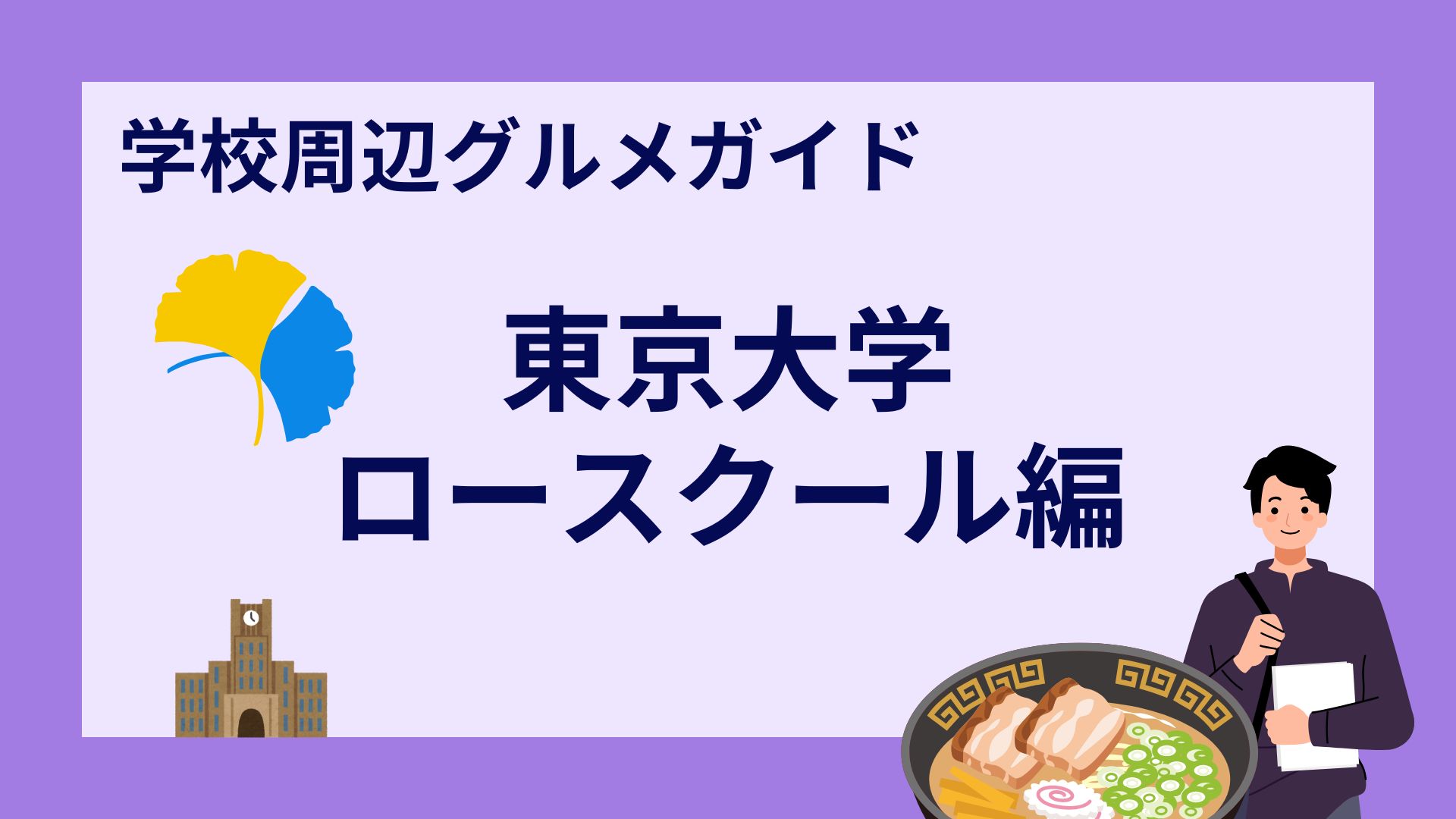- はじめに
- 法科大学院(ロースクール)ルート
- 大学の「法曹コース」で最短6年で弁護士に
- 予備試験ルート
- 司法試験
- 司法修習
- 終わりに
はじめに
弁護士は、社会の中で起こる様々なトラブルを解決します。紛争に巻き込まれた人の権利を守るため、代理人として交渉や裁判を行ったり、犯罪をしたと疑われる人が適切な手続を受けられるように弁護するなどの活動を通して、基本的人権を擁護し、社会正義の実現のために活動します。
では弁護士にはどうやってなるのでしょうか?
まず前提として、弁護士になるには司法試験に合格し1年間の司法修習という法律家になるための研修を修了する必要があります。司法試験、司法修習については後ほど詳しく説明します。そしてその司法試験は受験資格がなければ受けられません。その受験資格の取得方法は大きく分けて2つあります。
ではそれぞれのルートについて説明していきます。
参照:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/1422481_00021.htm)
法科大学院(ロースクール)ルート
まず法曹を目指すルートの1つとして法科大学院ルートがあります。法科大学院はロースクールとも呼ばれます。法科大学院を修了すると司法試験受験資格を取得できます。法学の知識をある程度有しているか否かで2つのコースに分かれます。それが既修者・未修者コースです。
既修者コースと未修者コース
- 既修者コース(2年):
法学既修者コースは、法律の基礎知識を既に修得している人を対象とする2年間のコースであり、法学未修者コースの1年目の課程が免除され、2年次の科目から学修を開始することになります。
- 未修者コース(3年):
法律の学習をしたことがない人などを対象とする3年間のコースです。1年目は法曹を目指すにあたって必要となる基礎的な法律知識や能力などを修得から開始します。
参考:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/mext_00963.html)
法科大学院在学中に司法試験を受験できる
前述の通り、従来は司法試験を受験するため、法科大学院の課程修了または司法試験予備試験の合格が必要でした。しかし、令和5年の司法試験からは、新たに法科大学院在学中でも司法試験を受験できるようになりました。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
- 所定科目単位の取得
- 法律基本科目(基礎科目):30単位以上(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
- 法律基本科目(応用科目):18単位以上
- 選択科目:4単位以上(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系・私法系))
- 卒業見込み要件
- 司法試験が実施される年の4月1日から1年以内に法科大学院を修了見込みであること
この要件を満たさず在学中受験ができなかったとしても法科大学院を修了することで、司法試験受験資格を得られます。
参考:法務省 (https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00097.html#%EF%BC%B1%EF%BC%91)
大学の「法曹コース」で最短6年で弁護士に
法科大学院在学中の司法試験受験に加え、大学での「法曹コース」を併用し早期卒業することで、最短6年で弁護士資格を取得できます。
法曹コースとは?
そもそも法曹コースとは法科大学院と連携し、学部段階から法曹資格取得に必要な学識や能力を身につけるためのコースです。法曹コースでは大学を3年で早期卒業し、法科大学院の既修者コースへ進学します。さらに法科大学院在学中に司法試験を受験し、法科大学院を卒業するのと同時に司法修習を始めることで最短6年間で弁護士資格を得られます。
特別選抜制度
次に法曹コースから法科大学院への進学について説明します。法曹コースから法科大学院へ進学する際、法曹コースと協定を結んだ法科大学院は、法曹コース修了予定者を対象として特別選抜を実施しています。
特別選抜には、「5年一貫型教育選抜」、「開放型選抜」があります。
- 「5年一貫型教育選抜」:
学部成績、面接等で選抜されます。
この選抜方法では、法律科目の論文式試験は課さないものとされています。
当該法科大学院と協定関係にある法曹コース修了予定者が対象です。
- 「開放型選抜」:
学部成績と論文式試験等で選抜されます。
当該法科大学院と協定関係にない法曹コース修了予定者が対象です。
参考:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houka/mext_00949.html)
予備試験ルート
2つ目のルートは予備試験に合格することです。
予備試験に合格すると司法試験受験資格を取得できます。
こちらのルートの方が、学校に通わなくてよいため楽だと思う方もいるかもしれませんが、予備試験は難易度が高く、最終合格率は毎年4パーセント前後となっていることからすれば、予備試験を経由して司法試験を受験することの難しさが分かります。
しかしその一方で予備試験合格者の司法試験合格率は近年90%を越しており、就職での優遇もあります。また誰でも受験が可能で、学校に通う必要がないため経済的負担を抑えることができるという利点もあります。
もっと詳しく予備試験について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

司法試験
司法試験受験資格を得たら、いよいよ本番の司法試験です。
司法試験は毎年7月中旬頃の4日間で短答式試験及び論文式試験を行います。
短答式は憲法、民法、刑法の3科目について行われます。
論文式は憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、選択科目の8つです。
司法修習
弁護士になるには、司法試験に合格するだけではなく1年間の司法修習を終えることが必要です。
司法修習は、法律実務に関する汎用的な知識や技法と、高い職業意識や倫理観を備えた法曹を養成することを目的としており、法曹養成に必須の課程として置かれています。
司法修習の最終試験(司法修習生考試)に合格して司法修習を終えることにより弁護士となる資格が与えられます。
参考:裁判所(https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/index.html)
終わりに
弁護士を目指す道は決して簡単ではありませんが、しっかりと準備し努力を続ければ夢を実現できます。
カケコム弁護士採用では弁護士の求人情報を随時公開しています!ぜひ最新の求人情報をチェックし、自分に合ったキャリアの可能性を探ってみてください。
配信登録もよろしくお願いいたします!